PROLOGUE
――なんで、ここにいるんだろう?
のっぺりしたニースの海を見ながら、ぼんやり考える。

自分の部屋を離れること、約1万キロ。目の前の水平線は、広げた両手よりも、長い。
時間は、朝の7時。日本では、午後の2時。
海岸脇の遊歩道は、幅が10メートルぐらいある。ジョギングする人、朝の散歩をする人、散歩させられている犬、観光客などでにぎわっている。
遊歩道の隣は、自転車専用道。きちんと区分けされてるためか、自転車は、すごいスピードで走っていく。
自転車専用道の隣は、右側通行の車道。自転車とは比べものにならない速さで、車やバス、オートバイが走っていく。
「……」
見回しても、制限速度を示す道路標識が見当たらない。
ぼくは、溜息を一つついてから、納得する。
――うん、ここは日本じゃない。フランスの南東部の都市、ニースだ。
続いて、さっきから頭の中をグルグルしている疑問を、もう一度、考える。
――で、どうして、ぼくはニースにいるんだろう……?
その疑問を片付けるには、2年ほど時間を遡らないといけない。
「次のクイーンの舞台はケニアにしましょう!」
講談社青い鳥文庫の敏腕編集者にして、はやみねかおる担当の山室さんが言った。
「いいですね、ケニア! それでいきましょう!」
打ち合わせは、この短い会話で終わった。
あとは、資料を集めて書き始めるだけ。そう思ったが、打ち合わせは終わってなかったのだ。
山室さんが、目を輝かせながら言う。
「ぜひ、ケニアに取材に行きましょう!」
――え?
冗談だと思った。でも、彼は真剣だった。
「物語にリアリティを持たせるためには、取材に行って、ケニアの空気に触れなければいけません」
力説する山室さん。
「いや……その理論だと、殺人事件を扱う推理小説を書く人間は、人を殺さないとリアリティが出せないことになりますけど」
反論すると、
「人を殺すのは悪いことで、罰せられます。でも、ケニアに行くのは取材であって、罰せられることはありません」
とても真っ当な意見が返ってきた。さらに、山室さんが熱く語る。
「地平線に沈むケニアの夕日を見たくありませんか?」
ぼくは山に住んでるから、毎日のように、山に沈む夕日を見てるしな……。わざわざケニアに行かなくてもな……。
「サバンナを駆ける野生動物を見たくありませんか?」
しょっちゅう、イノシシや猿や鹿を見てるしな……。
「ケニアに吹く乾いた風を頬に感じ、ウイスキーのオンザロックを飲む。これが、漢(おとこ)の浪漫だと思いませんか?」
『男』ではなく『漢』を使って、山室さんが言った。
50代になって、ますますデブ症出不精になったぼくは、これ以上会話を続けるとたいへんなことになると思った。
「大丈夫ですよ。ぼくが住んでる山の中も、ケニアみたいな野生の王国ですから――。もし書けなくなったら、そのときは行きましょう」
ぼくは、そそくさと会話を打ち切る。

前作『怪盗クイーン ケニアの大地に立つ』
その後、締め切りに追われるものの、平
穏な日々が続いた。
クイーンのケニア編も書き上げ、ぼくは
毎日、原稿を書いたり洗濯物を干したり草
刈りしたりしていた。
そして、今年の夏――。
「次のクイーンの舞台は、コロンビアにし
ましょう」
山室さんが言った。
――ころんびあ?
どこかの国名だとはわかったが、どのへ
んの国かは想像もできなかった。
ぼくが返事をする前に、他の編集者の方が、山室さんを止めた。
「コロンビアは、渡航注意が出てる国じゃなかったか?」
「そうだっけ?」
あっけらかんと答える山室さん。
このとき、ぼくがわかったことは二つ。
一つは、山室さんは海外へ行きたいということ。もう一つは、海外なら命の危険があるような場所でもかまわないということ。
ぼくは、自分の命を守るために言う。
「次の舞台は、熱海に決めました。『怪盗クイーン 熱海編』を書きます!」
「……」
山室さんは、とっても嫌そうな顔をした。
しかし、クイーンの原稿にかかろうにも、ぼくは『都会のトム&ソーヤ』の締め切りで苦しんでいた。
そんな中、ときどき、山室さんから連絡がある。
「熱海以外に、海外で、どこか行きたいところあります?」
「そういえば、この間、奥さんと『コートダジュールN゚10』というドラマを見ました。コートダジュールって、どこの国ですか?」
「コートダジュールは、フランス南部の保養地です」
「……」
呆れた感じが出ないよう、山室さんが口調に気を遣ってるのがわかった。
「でも、フランスなら、クイーンにピッタリです。よし、コートダジュールにしましょう!」
山室さんの明るい声。
ぼくは、熱海観光協会の人間になったような気持ちで発言する。
「熱海で、浴衣を着て射的をするクイーンも、似合うと思いますけど……」
「コートダジュールなら、ニース。そして、モナコ。カジノに現れる怪盗クイーン。うん、グッと来るものがありますね!」
「……」
山室さんの耳に、熱海観光協会の声は届かない。
しばらくして、また山室さんからの連絡。
「会社から、ニース出張の許可が下りました!」
「……マジですか?」
「マジです」
ニースというのが国名なのか地名なのか、確かめる気にならなかった。とにかく、『都会のトム&ソーヤ』の原稿ができず、ぼくは焦っていた。
「で、出発する時期ですが、10月末でどうです? さすがに、その頃なら原稿もできてますよね?」
「そりゃ大丈夫だとは思いますけど……」
「じゃあ、10月末にしましょう!」
「……」
ぼくは、自分の首に真綿が巻かれていくのを感じる。
「いや、山室さん、落ち着きましょう! だいたい、ぼくのパスポートは期限切れです。外国へ行けません」
「安心してください。パスポートなんか、すぐにとれます」
「ぼくは、フランス語はともかく、英語も話せない、日本語オンリーの人間です。こんな人間をつれてフランスへ行くのは、灯油をかぶって花火をするようなものです」
「大丈夫です!」
山室さんの力強い声。
そういえば、以前、山室さんに「ビストロ」の言葉の意味を教えてもらったことを思い出す。それに、フランスへも家族旅行で何度も行ってると話していた。
つまり、山室さんはフランスのスペシャリスト。言うなれば、フランス観光協会側の人間だ。
――ひょっとすると、有意義な旅になるのかもしれない。
こんなことを考えてしまった段階で、ぼくの逃げ道は、完全に閉ざされている。
「じゃあ、締め切り頑張ってください」
山室さんの明るい声。
そして、気がつくと、パスポートの申請も成功し、大きめのスーツケースが用意され、
「ニースって、寒いのかな?」
という奥さんの質問に、首を捻るようになっていた。
『都会のトム&ソーヤ』の原稿が完成し、担当編集者さんからOKをもらったぼくは、なるようになると思っていたのだ。
それでも、スマホに翻訳ソフトのアプリを入れたのは、少しは冷静な気持ちが残っていたのだろう。
「旅支度はできましたか?」
出発3日前――。
山室さんの質問に、ぼくは「完璧です」と答えていた。
「でも、いろいろご迷惑をおかけすると思います。なんせ、ぼくはフランス語わかりませんし、山犬をつれていくようなもんですから――」
「大丈夫ですよ、はやみねさん。ぼくも、フランス語わかりませんから」
「え?」
みなさんは、自分の周りで、空気の割れる音を聞いたことがありますか? もし聞きたいのなら、言葉のできない二人組で海外旅行を計画してみてください。きっと、あなたの周りで、ペキパキと音がすると思います。
山室さんが、黙り込んでしまったぼくに言う。
「心配ないですよ。ぼくも、はやみねさんに教えてもらったアプリを入れましたから」
「……」
ぼくは、山室さんとの会話を終えた後、コンピュータを立ち上げる。そして、『指さしフランス語会話』の本をAmazonで注文した。
配達日は、フランス出発の前日。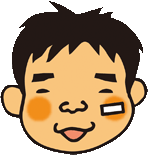
はたして、出国までに『指さしフランス語会話』は
届くのか? それは、神のミソ汁!
(結局、届きませんでした……)
これから「オーシャンズ2」のふたりに、どんな珍道中が待ちうけているのか……!?
次回更新は11月30日(金)予定です! お楽しみに!!




